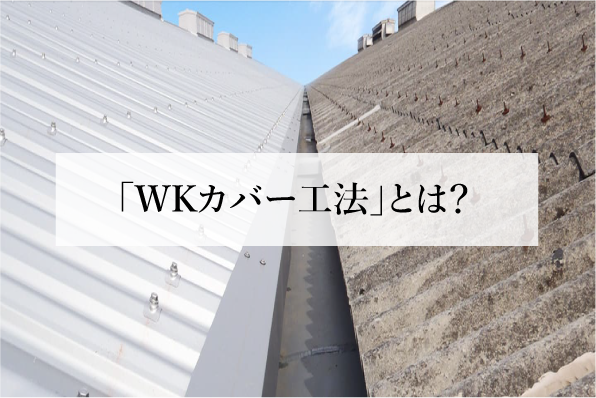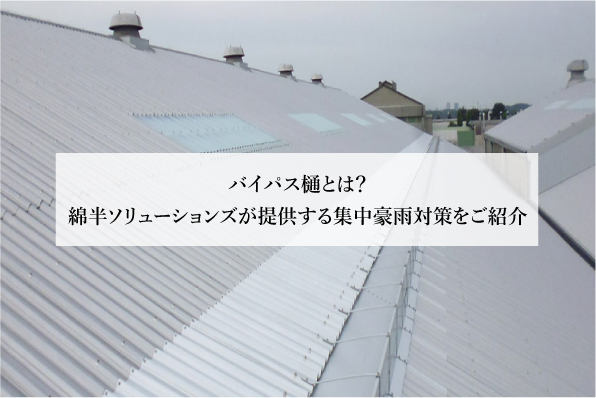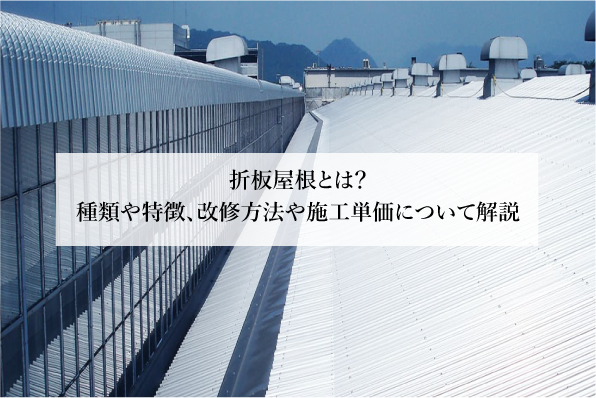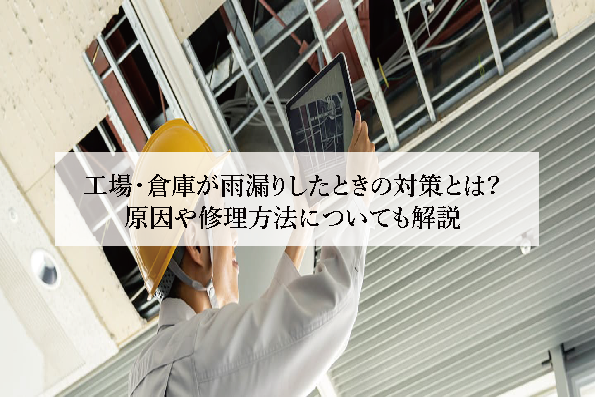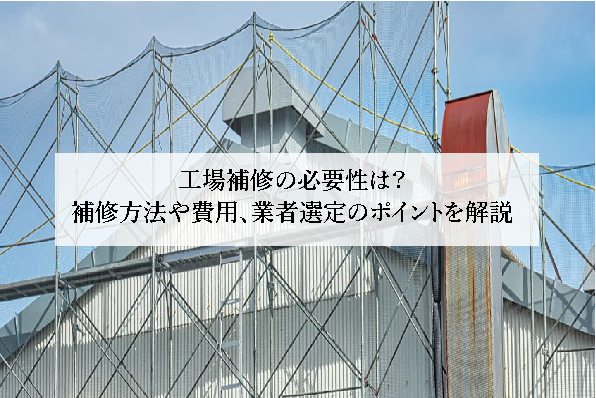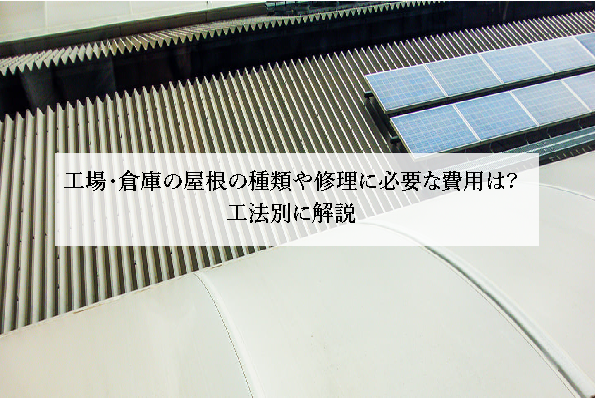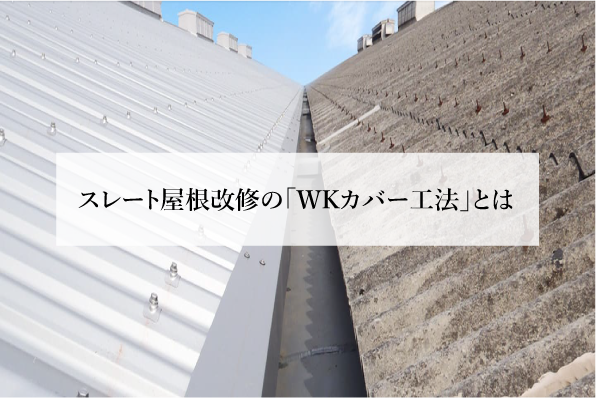近年、工場や倉庫ではゲリラ豪雨や台風による浸水リスクが増えており、事前の備えがますます重要になっています。
機械や在庫が水に浸かると、操業停止や高額な損害が発生する恐れも。
そんな被害を防ぐために効果的なのが「防水板(止水板)」です。
本記事では、防水板の種類や特徴を分かりやすく紹介しながら、現場に合った選び方のポイントも解説します。
実際の製品例や、水害対策を成功させるコツもあわせてご紹介しますので、導入を検討している方はぜひご参考にしてください。
なお、どの防水板を選べばいいかわからないと悩んでいる方は、現地調査から製品選定、設置工事までサポートできる当社にご相談ください。
建物の形状や用途に応じた最適な止水対策をご提案いたします。
詳しい対策については、以下の記事も参考にしてみてください。
浸水対策
工場・倉庫で設置できる防水板

防水板は、出入口や開口部からの水の侵入を防ぐための設備で、さまざまなタイプがあります。
設置が簡単なものや、自動で作動するタイプなど、現場の状況に合わせて選べるのもポイントです。
ここでは、特に信頼性が高く、多くの現場で導入されているおすすめの防水板をご紹介します。
ウォーターシャッター
ウォーターシャッターは、工場や倉庫の出入口に設置できる、手動タイプの防水板です。誰でも簡単に取り付けられる仕組みなのに、しっかりと水の侵入を防げる優れもの。
高さは377~1,960mmまで対応しており、幅は無制限なので、大きな出入口でも安心です。
寝ずの番
「寝ずの番」は、床に設置するフローティング式の防水扉で、水が入り込むと自動で扉が浮き上がり、すぐに浸水を防ぎます。電気を使わない仕組みなので、停電中でもきちんと作動。
ふだんは床と一体化して目立たず、フォークリフトの通行や作業にも支障がありません。
狭い場所や既存の建物にも取り付けやすく、まさに「眠らないガードマン」として現場を守ってくれます。
防水板の種類・特徴

防水板と一口に言っても、用途や設置場所に合わせてさまざまな種類があります。
出入口の構造や作業の動線、常時の使い勝手などを考慮して選ぶことが大切です。
以下に、代表的な防水板の種類と、それぞれの特徴をわかりやすくまとめました。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 起伏式 | ふだんは床に格納されていて、水害時のみ起伏させる。浸水してきた水の力を利用して防水板を起伏させる、浮力タイプもある |
| 脱着式 | 支柱にパネルを差し込んでロックする。設置が簡単で場所を選ばない |
| シャッター式 | ふだんは管理用シャッターとして使える、止水機能を持ったシャッター | シート式 | 軽くて、設置・収納が楽 | スライド式 | 横にスライドさせるだけですばやく止水できる。ふだんは戸袋スペースに防水板をしまっておく | 自動防水ガラリ | 水位が上がると自動で閉まる。ふだんは通気口として使用可能 |
このように、選ぶ防水板によって設置方法や使い勝手が大きく異なります。
現場の環境やリスクレベルに合わせて選びましょう。
防水板以外の工場・倉庫向け水害対策

工場でできる水害対策は、防水板の設置だけではありません。
ここでは、防水板以外の対策を3つお伝えします。
● 電気設備や制御盤を高所に設置する
● 土嚢袋を用意する
● 防災訓練をする
電気設備や制御盤を高所に設置する
水害時に特に注意が必要なのが、電気設備や制御盤の浸水です。電気設備が水に浸かると、感電や故障のリスクだけでなく生産ライン全体が停止し、長期間の操業停止や高額な修理費用につながる恐れがあります。
実際に、制御盤が浸水してラインが全て止まってしまった事例も少なくありません。
こうした被害を防ぐには、あらかじめ電気設備を床上の高い位置に設置しておくなどの対策が有効です。
設置が難しい場合でも、防水カバーをかけておくだけでも被害を抑えられる可能性があります。
土嚢袋を用意する
土嚢袋(どのうぶくろ)は工場や倉庫の出入口、排水口などからの浸水を一時的に防ぐための、シンプルながら効果的な対策です。コストが安く、場所を取らずに置いておけるため、多くの工場で採用されています。
実際に突然の豪雨で水が迫った際、あらかじめ準備していた土嚢をすぐに並べることで、水の侵入を最小限にとどめたケースもあります。
常に一定数を保管しておきつつ、ときどき設置訓練をしておくと、いざというときに浸水による被害を最小限にとどめられるでしょう。
防災訓練をする
水害に備えるうえで、防災訓練の実施はとても重要です。いざというとき、土嚢や防水板をどう設置するのか、どのルートで避難するのかを、従業員全員が事前に把握しておくことで、混乱を防ぎ、迅速な対応が可能になります。
特に、現場ごとに浸水リスクの高い場所を想定し、リアルなシナリオで訓練を行うことで、「実際に役立つ備え」につながります。
被害を最小限に抑えたい場合は、定期的に訓練していざというときに動けるようにしておきましょう。
工場の防水板に関するよくある質問

最後に、工場の防水板に関するよくある質問3つに回答します。
● 防水板と止水板の違いとは?
● DIYできる防水板は工場につけないほうがいい?
● 防水板の劣化を防ぐ方法は?
防水板と止水板の違いとは?
「防水板」と「止水板」という言葉、実はほとんど同じ意味で使われています。現場でも「止水板(防水板)」や「防水板(止水板)」と、併記されていることが多く、呼び方が違うだけと思って問題ありません。
土木関係では「止水板」、防災や設備系では「防水板」と呼ばれることが多いだけで、構造や性能には大きな違いはないのが一般的です。
選ぶときは名前より、性能や設置方法に注目しましょう。
DIYできる防水板は工場につけないほうがいい?
DIYタイプの防水板は、コストを抑えて導入できる点が魅力ですが、工場などの大規模施設にはあまりおすすめできません。というのも、簡易な作りのものでは、耐久性や止水性能に不安が残ることがあるからです。
もし浸水してしまえば、生産ラインの停止や高額な設備損傷といった深刻な影響が出る可能性も。
確実に工場を守るには、専門メーカーの信頼できる製品を選び、正しく設置・運用できる体制を整えることが大切です。
防水板の劣化を防ぐ方法は?
防水板を長く使い続けるには、日ごろの点検と保管方法がとても大切です。使用後は水分や汚れをしっかり拭き取り、直射日光や湿気の多い場所を避けて保管しましょう。
特に注意したいのが、ゴムパッキンの部分。ここが劣化すると止水性能が落ちてしまうため、ひび割れや変形がないか定期的にチェックし、必要なら交換しましょう。
ちょっとした手入れが、防水板の性能をしっかり保つポイントになります。
まとめ

今回は、工場や倉庫に設置できる防水板の種類や特徴、水害対策としての活用法についてご紹介しました。
防水板には手動で設置する脱着式や水の力で自動的に起立する浮力式、防水機能を備えたシャッター式など、現場の状況に合わせて選べる多様なタイプがあります。
また、土嚢の準備や防災訓練などと併せて対策を行うことで、より実効性の高い水害対策が可能になります。
もし「自社にはどのタイプが合うのか分からない」「建物にどう設置すればいいか不安」という場合は、専門の業者に相談するのが安心です。
綿半ソリューションズでは、現地調査から設計提案、施工まで一貫してサポートしています。
建物や用途に応じた最適な止水対策をご提案しますので、ぜひ以下のページから詳細をご覧ください。
浸水対策